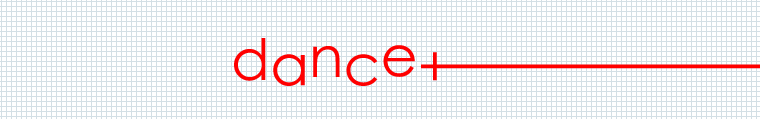
| 日々是ダンス。踊る心と体から無節操に→をのばした読み物 |
|
|
|
34 アジアの現在 LIVE ARTS BANGKOK
■ キュレーションの特徴
芸術観がイニシアティブを取る場というのは、あるひとつの視点から論理的な一貫性をもってプログラムが組まれていることからも分かる。それを、私はキュレーションと呼んでいる。SEAMEO-SPAFAが組織として主催している事業である以上は、組織としてのミッションからはみ出さないということは前提であるが、そのことがフクワン自身の関心と重なっているという幸運もあり、比較的思い通りのプログラムが組めたのではないかという印象がある。
アジアの舞台芸術を語るとき、「伝統と現代」というテーマを立てることで、過去の遺産と今あるものを非連続しているものとして扱うやり方をしばしば目にする。が、現実をよく見ると、実は私たちの生活はそれらの要素が混在しているのではないか。批評精神に溢れ、もともとドラマトゥルグ(*註3)を目指していたフクワンのプレゼンテーションの方法は、古典だ、現代だ、というステレオタイプのものの見方をすべていったんゼロにして、積極的に自分の切り口を提示するものである。ときには作品を見せる工夫というより、演出といった方が近い作業にも携わる。
具体的には以下の切り口から、キュレーションの特徴を見ることができるのではないかと思う。
1)古典のプレゼンテーションの方法を提示する。
まず、このフェスティバルを印象的にしている一番の特徴は、古典の提示の仕方に工夫を加えた点であろう。テーマに遺産としての芸術の再生を掲げている以上、それをどのように実現させるかがキュレーターとしての腕の見せどころというものだ。そこで、カンボジアの古典舞踊の踊り手であるフン・ペンとオリッシーダンスの踊り手であるマレーシアのジャニュアリー・ローの「シーン・サイレント(Seen Silent)」という作品を例に挙げながら説明したい。
この2人は、同じ日に生まれたという共通点を持つ若い女性の古典舞踊の踊り手であるが、この2人を選び、作品に枠組みを与えたのはフクワンである。
舞台の上に、それぞれの踊りの衣装をつけた2人が現れる。彼女たちは、リラックスして床にベタっと座り、互いについての質問をする。「どうして古典舞踊を習うことになったの?」「どうやってトレーニングしたの?」というダンサーとして会話から、「ボーイフレンドいる?」「古典的な女性像を踊るって、気恥ずかしくならない?」「古典の衣装を着けると、どんな気分になる?」というような普通の女の子の会話に至るまで、幅広い質問と答えがかわされる。その合間に、「私の習ってきたダンスはこういうものなの」と言いながら、それぞれの踊りを披露していくのである。
現実とは切り離された別世界と思われがちな古典舞踊の世界に、彼女たちの現在の時間と生身の生活のイメージを重ねていく。そこには伝統と現代という二項対立はなく、いくつもの時間が彼女たちの身体を現場として多層的になっているのが見えてくるのである。このような枠組みを与えることによって、コンテンポラリー・ダンスには興味があるが、古典は古臭くてつまらないものだと思っている観客層に、古典をとっつきやすく、アクセシブルにしている点が有効であると思う。
異なったジャンルの踊り手同士に対話させ、それ自体を作品とするという方法論は、フクワンはすでにタイのピチェ・クランチェンとフランスのジェローム・ベルを起用した「ピチェ・クランチェンと私」という作品で実験済みである。今回は、その女の子バージョンと考えていいと思う。ピチェたちの作品も非常に知的で刺激的だったが、今回は現代の女性が古典的な女性像を担うことの居心地悪さを白状するなど、女性ならではの視点が出てきたのがおもしろかった。
2)新しいアートフォーム
ふたつめの切り口は、新しいアートフォームの提示ということである。それぞれの国には、いわゆる現代演劇もダンスもあるが、そこを敢えてはずしてきている。特に私がおもしろいと思ったのは、シンガポールのスペル#7とマレーシアのファミ・ファジルの作品である。スペル#7のポール・レイの作品は、シンガポールに樹齢が長い木がないという発見をした、ということを発端に地球の環境問題にまで言及するスピーチである。演じるのではなく、やはりどう見ても観客に話しかけているスピーチなのだ。だが、ポールというキャラクターが醸し出すどことなくインチキくさい雰囲気が、真実と虚構をないまぜにする。今まである演劇の一人芝居が虚構を現出させるときの手法だとしたら、ドキュメンタリー演劇を一人で演じる場合の手法はこうなるのかと、思わず深くうなずいてしまった。
また、マレーシアのファミ・ファジルは、アコースティックギターを弾く相棒とワヤン(影絵)をつかって、本をめぐる寓話を一人芝居で演じた。その中では、インドの古典「ラーマーヤナ」とNHKに映った(という設定の)KAT-TUNが同等に扱われる。まさか、ここでKAT-TUNの名前を聞くとは思っていなかったので、私は椅子から転げ落ちるほど驚いた。同時代などということばでは、もう彼と私の現実は言い表せない。現実の一局面ではあるが、それこそ「同時」である。自分の日常的な生活が「アジアの舞台芸術」の中にいきなり出現したことが衝撃だった。どうして今までそういう作品に出会わなかったのだろう? 現実には、アジアの中でポップカルチャーの交流の量とスピードはすさまじく、私自身もフクワンを含む友人たちとも映画や音楽のミーハーな会話を楽しんでいるのに。今までの私たちは、どこかまだ舞台芸術をハイカルチャーとして、ポップカルチャーから切り離して考えていたのかもしれない。化学技師だったというファミは、そういった先入観から自由である印象を受けた。語る内容が変われば、語る手法も変わってくるのだ。
(*註3)上演芸術の実現にあたり、主にテキスト分析や理論の吟味を担当する。もとはドイツの劇場における演劇部門の文芸部を指したが、上演芸術全般におけるドラマトゥルギー概念の拡大にしたがい、ダンスなどにも適用されるようになった。『シアターアーツ』2007年秋号所収、中島那奈子著「ダンス・ドラマトゥルグ」を参照のこと。
|
|
|

|