 |
 光島さんは、視覚障害者と晴眼者による美術鑑賞ツアーを行う"ミュージアム・アクセス・ビュー"のメンバーでもありますが、これはどういう経緯で? 光島さんは、視覚障害者と晴眼者による美術鑑賞ツアーを行う"ミュージアム・アクセス・ビュー"のメンバーでもありますが、これはどういう経緯で?ミュージアム・アクセス・ビューの立ち上げに関わったメンバーが僕と阿部さん、鳥養さんとか、その辺の人達なんです。要するに設立メンバー。 設立のきっかけは? 2001年に京都で「人・アート・まち」という芸術センターで行われた展覧会があって、そこに僕の作品を出してもらったんですよね。その流れで、視覚障害者の人達にも来てもらおうと考えた時、どういう形式がいいのか?って。僕の作品は触れますが、他の人の作品も楽しんでもらおうと。それじゃ、言葉で鑑賞するということをワークショップ的な試みとしてやってみましょうか、ということになったんです。その頃はまだ準備会的なグループだったんですが、次の年の2002年くらいから、本格的に活動しはじめました。 私はミュージアム・アクセス・ビューのことを知った時、やっぱり何のことなのかわかんなくて"絵を言葉で?""何やそれ??"みたいになってました。でもその後、自分でも視覚障害の人向けのワークショップをするようになって、自分なりに考えて文脈を積み上げていったら"なるほどねー"って、納得したんですよ。 ミュージアム・アクセス・ビューも僕の活動の側面ではあります。つくるっていうことと作品を鑑賞するっていうのは表裏一体だと思うので。もともと"野外彫刻を触ってみたい"という欲求から、僕の場合スタートしてますので、美術館に行っても"何で触らしてくれへんのや?"っていう問い掛けから入っているんですよね。実は、最初は言葉で説明されることに対して、ものすごく抵抗があったんですよ。説明するくらいやったら触らしてくれやー、って。でもそうは言っても、彫刻とかは触れるけど、絵とかは触れないわけで"触らしてくれ"って言ってるだけでは埒があかへんなと。そのあたりが、今のミュージアム・アクセス・ビューの活動に繋がって行くんですよ。言葉で説明するっていうのも最初は"こんなんでホンマにわかるんかな"って思ってたけど、やってるうちにね。まぁええかと。実は、これも古い経験というか原体験が蘇ってきたところがあって。思い出してみると、小さい頃に母親にいろんな所、例えば博物館とかに連れていってもらっていたんですよね。母親は僕がなるべく触れるようにしてくれていたんですが、やっぱり触れないものもあって、そんな時は言葉で説明してくれていたんですよね。だから、別にはじめてやったことじゃなくて、子どもの頃から普通にやってた事をシステム化するってことなんだろうなと思っています。 言葉を使った美術鑑賞というのは、視覚障害者の側から見て、面白いものなのでしょうか?説明する側のスキルとかにも左右されますよね。 僕の場合はかなり特殊だと思うんですよ。自分が作家だから。僕は、こういうことについて聞きたい、というのが割とあるので、積極的に聞いていく姿勢なんです。この間、富山で美術鑑賞ツアーに参加したんですが、身体について今いろいろ思うところがあるので"こんな作品をつくってるんやけど、似た作品はないか探してくれ"って言って。 アクティヴというか、つっこみまくり。 結論から言うと、似た作品はなかったんですね。で"こりゃええな。僕が最初や!"って。 わははは。しめしめですやん。 わはははは。そうそう。 ミュージアム・アクセス・ビューの仕組みをつくる側から見て、視覚障害をもつ参加者の反応はいかがですか? 多くは「ようわからんけど、来てみて、体験してみたら、面白かった」っていう反応ですね。でも、もどかしく思う人もいると思う。見えていた時の体験が逆にあったりすると、説明してもらえばもらうほど見たくなる。自分の目で見たくなる。 フラストレーションを余計に感じてしまうんですね。 確かに一緒に回る人によって、体験は変わってしまうけれど。とにかく"美術館という所で、これに参加することで、何か面白いことがあった"って、喜んでもらえてるのかなぁ、と思います。 考えようによってはミュージアム・アクセス・ビューのやっている事って、かなり冒険的なことですよね。人間の認識の問題とコミュニケーションの問題を同時に再確認するような側面があると思います。地味と言えば地味ですが。 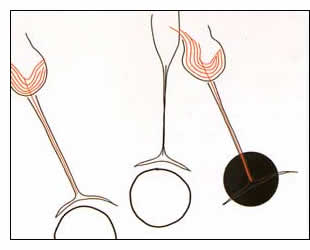 新しい鑑賞方法だとは思っています。 新しい鑑賞方法だとは思っています。表現と社会性というのはどう思われますか? 僕が紹介される時って、いくつかの切り口というか、顔があると思っています。ひとつは"障害者アート"ということで括られて、紹介される場合。障害者の芸術祭とかエイブルアートって言葉なんかもそういう括りですよね。もうひとつは"アウトサイダーアート"。これは僕が思うに、現代アートの枠組みの中で、そのインサイドに対してのアウトサイドっていう面がちょっとだけ障害者アートという括りとは、違うような気がしてるんですよね。あと、もうひとつは"視覚障害者の作家"という括り。障害者アートよりはもうちょっと狭い括り。これらの括りで紹介される中では、障害者アートとして紹介されることにすごい抵抗があったんですよ。はじめっからそういう切り口で紹介される事の方が多いし。長野アートパラリンピックなんかで賞をとったっていうのもそうなんですけど、賞をとっときながら、何となく、こう。 わはははは!勝手やなー。 わははは。まぁ、それだけじゃない所でも紹介してほしいなって気持ちがすごいあって、どうしても付きまとってくるものとして嫌だったんですよ。99年に「SKIN-DIVE」っていう展覧会が京都であって、そこは現代アートの作家のひとりとして紹介してもらった。今回のサンディエゴもそうなんですけどね。僕の作品が"アウトサイダーアート"の一種として捉えられているのかなぁって。その方が何ていうか、一般のアーティストと肩をならべあっているというか、同じ作家として扱ってもらってる感じなんで、これはいいかなって思いました。それ以後、障害者アートって括りの展覧会、アウトサイダーアートって括りの展覧会、視覚障害者の作家としての展覧会と、それこそバランス良くあっちこっちに作品を出すようにしています。そんなバランス感の中で、最近思いなおしてみたことは、所謂、障害者アートっていう括りの時に、気持ちとしてはほっとする所があるなぁって。肩ひじはらずに出来る。何でだろう?って考えてみたら、まわりが障害者ばっかりということではなくて、関わっている人がやっぱり福祉関係の人であったりするのは、まぁ問題もあるんやけど・・・。 文脈はちゃんと共有できてる。 そうそう。僕自身が見えないということも理解した上で関わってもらえるんで、楽なんです。そういう良さもわかるようになってきましたね。それとは逆に、さっき言ったアウトサイダーアートっていう形で、現代アートの人の中に入っていく時には、挑戦的な気持ちになるんですよね。それはそれでまた面白い。ひとりの作家・光島貴之として、なおかつ見えないということも含めてあたり前に紹介される、っていうのが一番に目指すところかなとは思うんですが、なかなかそこまではね。 光島さんはクラシック音楽がお好みのようですね。脱線しますが、アメリカの初期のブルースミュージックがアウトサイダーアートとして評価されています。初期のカントリーブルースを演奏していた黒人ブルースマンというのは、盲目の人が多かったんですよ。"ブラインド何とか"みたいな。一体何人おんねん!みたいな。 ははは。はいはい。 彼らは所謂楽譜は使わないわけですよ。話言葉のリズムから膨らんだような小節感覚や音程をもっていて、聴きようによっては、非常に美しい音楽がいくつも録音され、現在のポップミュージックの基礎になっている。光島さん!流れはアウトサイダーアートの方にありますよ!テープをつかった絵画の開祖として、来世紀ぐらいにものすごく偉い人になってたりして! わはははは。 |
|