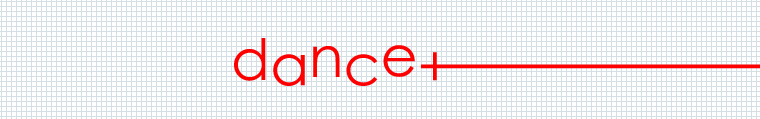
| 日々是ダンス。踊る心と体から無節操に→をのばした読み物 |
|
|
|
|
祭りと“フェスティバル”の現在(1)
アートを受けとめる身体と言葉
Text:メガネ
■ 祭りの風景
子供の頃、地域の秋祭りの頃になるとなぜかそわそわし、お兄さんお姉さん世代の活躍をまぶしく眺めたものだ。そこでは、近所で不良と恐れられている兄ちゃんが急に生き生きして地区をとりしきり、にわかカップルがぼこぼこできた。祭りにおいては、階級差や性差が転倒し、違いを越えて人々が結びつく非日常の空間があらわれる。人類学の授業かなんかでそう習ったときは、なるほどと思ったものだ。
■ フェスティバルの風景
今日、こういった社会のリフレッシュ装置としての祭りと、演劇祭や音楽祭といった芸術祭の“フェスティバル”の風景は、一見かけ離れている。だが多くの芸術祭は、人と人とのつながりや、循環する時間とのつながりが失われた都市において、祝祭的な空間を新たに生み出そうという考えをルーツに持っている。よく知られているザルツブルク音楽祭などが、その代表格である。
■ アート・フェスティバルの体験
この近代のフェスティバルも、地域や時代によって様変わりする。アート界の“惑星直列”と呼ばれた昨年、カッセルの ドクメンタ、ミュンスターの 彫刻プロジェクト 、ヴェネツィアの ビエンナーレ を初めて訪問した。そこで印象的だったのは、経済効果が重視され、「アートの見本市」、「アートの大量消費」と批判されて久しい今日の芸術祭で、“消費者”の側で体験を活性化する現実的なしくみと、そこでの言葉の役割だ。その体験を振り返って、ダンス・フェスティバルの現在のあり方について考える導入としてみたい。
|

| | |
■ 旅することと地図を身体化すること
まず、都市をあげてのフェスでは総じて、めちゃくちゃ歩かなくてはならない。美術館通いやギャラリーめぐりを常にしている人は、なーんだ、と思われるだろう。でも幕の上り下りで切り取られた時間、客席で身じろぎもせずということばかりしている筆者には、それだけでも新鮮な体験だった。歩きながら作品と都市の風景を交互に味わう。都市の内外にスケールの大きな彫刻が散在する会場では、自転車を借りてそばまでゆき、作品に応じてさまざまな位置や姿勢を試しながら見る。市民の生活の場に作品が挿入されていたり、常設展の中に新たな作品が“隠されて”いたりすると、見るべきものは見つけ出されなければならない。よく、美術館や劇場を出た後で日常が違って見えるということが言われるが、このツアー中は、日々刻々と新しいメガネを手にする思いだった。その中で、アートマップを読み、都市の凸凹を体感し、さまざまな地域と歴史に背景をもつ作品を鑑賞することが複雑に結びついて、体の中に地図をなしてゆく。
■ 作品をきっかけに交わされる言葉
旅に伴うこのような行為は、作品への能動的なかかわり方という意味で、鑑賞者に促される最低限の参加ということが言えるかも知れない。けれども、1人静かに鑑賞行脚を楽しみたくとも、道中の不幸と幸いが、さらなるアクションへと旅人の背中を押す。例えば、作品があるはずの場所でそれらしきものに出会えなかったとき、「なかった」ことにしてしまうのは、足を運んだ駄賃を考えてももったいない。自分の背中を押して、「ここの〜、どこが〜、アートなんですか?」と、通りすがりの人に聞いてみる。あるいは、出会った作品について、そこいらにいる人にちょっとした質問をする。たいがい、違うやり方で作品に出会った人から、期待を上回る量の説明が返ってくる。ふと気がつけば、作品に動かされた過剰な言葉で溢れかえった街中で、見知らぬ人々の言葉に、次第に耳がチューニングされてゆく。
こういった過程で気づかされるのは、ほとんど対話のきっかけにすぎなくとも、違う価値観を交換する手がかりとして作用するアートのあり方だ。そしてこのことは、お国柄の違いといった話ではなく、近年のアートの動向全般とも無関係ではない。
■ ドクメンタの椅子
その動向を象徴しているように思われたのが、ドクメンタだった。この、良きにつけ悪しきにつけ現代アートの市場動向を左右するアートフェスの代表格が、このところ、たくさんのお金をバックに一部の人によって価値が操作されるアート市場に対する批判的な方向性を打ち出しているということは聞いていた。(その背景については、カレイドスコープのプロデューサー、北川フラム氏の、 『plug 007』におけるインタビュー記事がわかりやすい。)第12回目のドクメンタが打ち出したのは、さまざまなかたちでのフォーラム(議論の場)づくりだった。それは、作品の選択や配置にとどまらず、世界中のアート雑誌と提携して行った出版プロジェクトや、連日催されるワークショップやレクチャーというかたちで表現されていた。特に印象に残ったのは、展示会場のあちこちに美術品を異化するかのように置かれた椅子の群れだ。コの字型に配置されたそれらは、明らかに休憩用ではなく、会場での自発的なフォーラムへと鑑賞者を誘っていたのである。
|

| | |
■ ダンス・フェスティバルの可能性
さて、このように祭りは、異なる価値観の交換の場へと姿を変えようとしているように思える。例に見たのは海外のアート・フェスティバルだが、同じ傾向は1990年代後半以降のダンス・フェスティバルや、さらに奇しくも今年のアルティ・ブヨウ・フェスティバルのアフタートークの方針などにも見てとれる。ここで、「これがインターナショナルなトレンドである」などと言いたいわけではない。“良い”作品を提示して、多様な地域、社会階層、立場の人々を感性的に結びつける。そんな近代フェスティバルの理念も、多様な作品がグローバルに流通する傍ら、価値観の形成と結びついた資本が再編される中で、必然的に変化を被っているのだ。そこではアートは、束の間共同体を生み出す美的な快や趣味だけでなく、多様性を包みこんだ人々の間に議論を呼び起こす装置にもなる。そういった可能性を認めて、ふだん行く劇場でダンスを見るとき、自分が見ることを「オフ」にし、誰に問いかけることもなく、閉じた身体で、目の前の身体を浪費しているのではないだろうかと自問されるのだ。
■ パフォーマンスとしての言葉
最後に、このようなアートの動向に応じて、もっと試みられてもよいと思えるのは、パフォーマンスに参加する言葉の様々なかたちではないだろうか? 作品が備える批判性への応答としての批評、価値観の調停法という意味での対話など。先月からdance+には、予め示し合わせることなく、これら言葉のパフォーマンスに配慮した記事が寄せられている。こういった個人の動き方ひとつにも、目の前の身体を豊かにする、多様かつ他の価値観を排除しない言葉のあり方が、いろいろなところで探られていることを知ることができる。
|
|
|

|