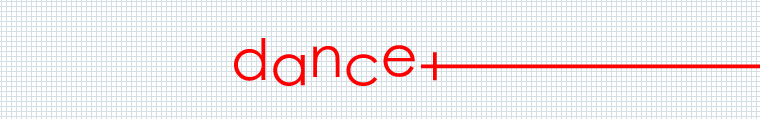
| 日々是ダンス。踊る心と体から無節操に→をのばした読み物 |
|
|
|
|
作品紹介とインタビューによる「あなたのダンス」2
『船乗りたち(陸地バージョン)』山下残
|

| | |
|
『船乗りたち』とは?
一昨年、京都芸術センターで初演された『船乗りたち』の改訂バージョン。元バージョンは、自分たちの体重移動によってぐらんぐらんに揺れ動く木組みの筏の上でコレオグラフィーを遂行していく、一見無茶とも思える実験でした。正確には、テクストとしてのコレオグラフィーが絶対再現できない条件を設定し、その中でコレオグラフィーを成立させるという負荷を課せられたダンサーの身体から、再現を越えた生を立ち上げようとする野心的な試みです。はたして私の見た回では、山下さんが率先して筏を揺らしていた印象が勝って、彼の挑発に拮抗するダンスが生まれたのかが疑問として残っていました。
本気モードを引き出す仕掛けはどこに?
では、今回陸に上がった船乗りたちは、自由という不自由から出発して、この疑問をどうやって払拭してくれたのでしょうか。
まずは初日の感想から。揺れない床でわざわざよたよたしながら踊っているように見えたのは最初だけで、ダンサーたちの本気モードに引き込まれるのに時間はかかりませんでした。けれども不思議なことに、本気モードを引き出す元バージョンの筏にあたる仕掛けが見えません。そこで、山下さんのこれまでの作品の流れの延長で、解放のスプリングボードとなってきた「制約」のようなものから押さえると、やはり決められたテクストを遂行するという縛りは一つの要となっています。次に、このテクストの遂行を目に見えて妨げているのは…ダンサー同士がお互いに足かせになっている、ハードなコンタクトくらいでしょうか。その様子は、一見プロレスっぽく見えるのですが、攻撃の中で生まれる真剣さとはやっぱり違う…ということで、むしろ、これまでに見たコンタクトの中で最も空恐ろしかったボリス・シャルマッツ*の2000年の作品が思い出されます。けれどもダンサー同士のコンタクトは後のほうで、まばらに見られるだけなのです。
*日本では、下半身に着衣がなかったために検閲が入り、パンツを履いて上演された『アタンスィオンAttention!』の来日公演で知られるフランスの振付家。2000年の作品では、ボロ布にくるまれたダンサーたちがお互いを荷物のように扱うコンタクトを展開。なぜわざわざ日本ではあまり知られていない振付家を参照するのかは、最後に説明させていただきます。
身体化された仕掛け
ダンサーたちがさらにはじけた最終日の公演を見たときに、作品のもう一つの要となる仕掛けが見あたらないわけがわかりました。ダンスとしては至極当たり前のことなのですが、本気モードは、ダンサーたちが「揺れる床」を身体化したことによって生み出されていたのです。観客の身体と近い素の状態から始まって、あたかも平衡感覚を司る神経系統が徐々に壊れてゆくかのように、ダンサーたちはコレオグラフィーをなぞることができなくなってゆきます。その果てに、オフ・バランスから自らの体重にまかせて暴走し、壁か床かお互いの体に触れることでしか、安定を保つことができなくなってしまうのです。彼らが必至の形相で仲間にしがみついていたのも無理はない。
このように、今回、『船乗りたち』の実験が実を結んだ一番大事な要因は、どんな練習をしたのやら、ダンサーたちがこの奇態な身体技術を体得し、自らの身体とテクストという二重の足かせの狭間で格闘したことにあります。特に大槻さんと川崎さんが、振付家として共演者として2人を挑発し続ける山下さんに、冷静かつ真剣に挑んだ結果、観客は、通常なら同じ作品の再演を追いかけたり、リハーサルに長くつきあったりしなければ出会えないような、ダンサーがハードルを「越える」瞬間に立ち会うことすらできたのです。このような瞬間を、即興ではなくコレオグラフィーにより舞台で出現させる方法を発見したことは、舞踊史的にみても貴重な収穫だと言えます。
|

| | |
|
『船乗りたち』への応答あるいは余談
さて、作品紹介としてはここで終わりなのですが、もう少し『船乗りたち』に考えさせられたことを展開してみたいと思います。初日に「見あたらなかった」事柄、つまり筆者が筏に変わる仕組みを鑑賞の間中探し続けたということから、考えてみたいことがあるからです。
探しものは、本来ダンスを見る際にそこが見えなくてはお話にならない身体技術の中にありました。柔軟な視点でダンスを鑑賞する人ならすぐに見えたでしょうし、またそれがどのような仕掛けであるかなんて考えなくても、その結果に引き込まれたことでしょう。
ならば、筏に限らず、先に見たような輝かしい瞬間へと導く目の前の出来事がどのような仕掛けやコンセプトにもとづいているかを、なぜ鑑賞の間中考え続けなければならなかったのか。それは『船乗りたち』という作品から導かれる必然だと言うしかありません。というのは、結論へと飛ぶと、技術やスタイルにおいて既存のいかなるダンスからも遠いこの身体表現が、劇場で鑑賞者のために行われているダンスの取り組み以外のなにものでもないからです。これは、美術館に置けばなんでもアート、という風に誤解されている制度論の延長で言っているのではありません。『船乗りたち』には、舞台から切り離され、かつ共同体に属する身体技術を一つとして共有しない複数の観客に身体のリアリティーを与えるという、コンテンポラリー・ダンスのアポリアへの真摯な取り組みが認められると言いたいのです。
その根拠の一つ。まず不思議なのは、『船乗りたち』の身体が、ダンスとして見ても身体イメージとして捉えても、つまり芸術的あるいは社会的な身体技術という観点から、決して魅力的、あるいは規範的なものではない点です。さらにそれは、「わざわざよたよたしている」ように見える、つまりほとんど素の状態から変化してゆく様子を見せてゆきます。なのでその結果は、様式史から抜けられない目が知覚する、「自由でとらわれないスタイル」ですらない。これを、非日常の美的に洗練された身体技術としてのダンスに対する批判として読むことは簡単なのですが、大事なのは、なぜそのようなことをしてダンスが生み出されなければならないのかという点です。
もう一つ。予め決められたコレオグラフィーの扱いもユニークです。一般に、ダンス「作品」の始めと終わりを決め、作家性の証明ともなるコレオグラフィーは、アートであるためには重要な再現テクストです。それをなぜ壊す?確かにそれは、ダンサーにとっては制約でもあります。けれども通常のダンス作品では、コレオグラフィーを身体化した時点でダンサーは解放されるのではないでしょうか。それが『船乗りたち』では、その解放の足かせとなる「筏」をさらに身体化して、ダンサーはがんじがらめ、テクストはぼろぼろ。もちろんこの二重の負荷を乗り越えたダンサーたちの演技を、芸術作品の自律性や作家性の基盤となるテクスト批判として読むことは簡単なのですが…以下省略。
話を戻して、なぜダンス作品に考えさせられなければならなかったかという点から押さえておくと、単純に、『船乗りたち』の成功の鍵となった身体技術や演技が、ダンスからかけ離れたところを遠回りして得られたものだったからです。そのことは、上の2点にとどまらない謎となって、作中に提示されていました。そして、一つ一つの謎は、既存のダンスに対する問いかけ、あるいは批判と読み替えることができるのですが、批判そのものを目的としているのではなく、より深い問題意識に根ざしているので、遠回りにつきあわなければという気にさせられる。ではそれは何か?という問いに対して、本来なら他の作品も参照したりして踏まなければならない手続きを省略すると、こういう言い方ができるかと思います。
いくら見目麗しいお兄ちゃん/お姉ちゃんがクールなコレオグラフィーをブリリアントに踊ったところで、ダンスは成立しない。
つまり、現代の劇場において、そこにいる人々が一体化して浄化されたり解放されたりするような瞬間を得ることは不可能、少なくとも並のやり方ではダメだという認識に、『船乗りたち』の批判は根ざしていると考えられるのです。この認識からは壮大な舞踊史リンクが生まれるのですが、そう考える理由を説明していないので、機会を改めることにして、結論に戻りましょう。
先に「真摯な取り組み」と言いましたが、本作は、既存の芸術舞踊を成立させている価値観に対して批判を加えつつ、なおも芸術という制度の内部でダンスの可能性を求めた結果、成功した試みだと理解されます。
こう結論づけることが、作品が投げかけてくる謎との対話ではなく、予備知識による作品要素の読み替えの結果として敬遠されるのであれば、この応答は失敗です。そして、これが失敗する可能性は高いだろうな〜と思いながらも長々と余談を続けてきたのは、『船乗りたち』が、国内マーケットでは、格闘技系やお笑い系のアナロジーに回路づけられ、ダンスの取り組みとしてはせいぜい、自由な発想にもとづく珍奇なスタイルとして消費されてしまうのではないかという危惧があるからです。もちろん、「マーケット」であるということを自覚して、ダンスに無縁の人々へ作品を開く戦略として、ダンスの身体技術や身体表象をポピュラーなものと関連づけるのは大事な仕事で、その方向での成果はあがりつつあると思います。けれども、『船乗りたち』の可能性は別のところにあります。というのは、上で見た批判的な取り組みが、西洋近代の舞踊史が権威を失った1990年代以降の世界各地のコンテンポラリー・ダンスと、深い所で問題意識を共有し、かつその問題に一つの解答を示しているからです。具体例を挙げるなら、『船乗りたち』には、先に挙げたシャルマッツや、ジェローム・ベル*という振付家の仕事ととても近い批判性が認められます。そして、彼らを引き合いに出すのは、海外のトレンドとの類似を指摘して価値づけをするためではなく、ベルの作品が、批判理論の一般的な受容に支えられたダンスのシニシズムにとどまっているように見受けられるのに対し、『船乗りたち』は、シニシズムを乗越えたところに、ダンスに可能性が残されていることを示し得たからです。
その意味で、陸の『船乗りたち』は、もっと広くて深い海に漕ぎ出して、同じ問題意識を持つ作家を勇気づけてゆく作品になるのではと考えられるのです。
*フランスでは 「ノン・ダンスnon danse」と呼ばれ、アジア・ダンス会議のタン・フクワンさんの発表では「言説的ダンスdiscoursive dance」と紹介された、身体表現とそれに対するコメントを併置して、踊ることや身体にまつわるポリティクスに気づかせる仕掛けを仕込んだ作品群の代表的な振付家。日本では、『シャートロジーShirtology』という、演技者が重ね着したプリントTシャツを延々脱いでゆくだけの作品が上演されています。
山下残さんのインタビューについては、今回時間が足りなかったので、『船乗りたち』元バージョンの前に行った 『空腹の技法その2』をご参照いただければと思います。
|
|
|

|