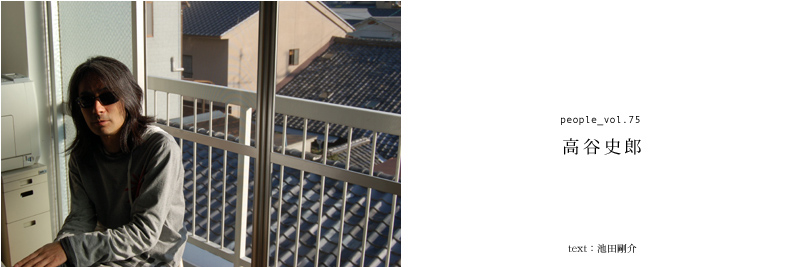高谷:「photo-gene」の最初のイメージでは、とにかく白黒写真を使って作品を作りたかった、というのがあります。というのは、今まで色々な「イメージ」に関わって作品を作ってきましたが、写真というのはその間、ずっと惹かれるマテリアルだったんですね。写真というのはモノじゃないですか、最終的には。情報は薄くのってるんですけど、紙というマテリアルが美しい=カッコいい。限りなく平面に近いんだけど、立体作品ともいえる。
 その前の児玉画廊(大阪)で発表した「Camera
Lucida」という作品を今回ドイツで展示してきたんですが、レンズとスクリーンだけがあるというような作品で、再展示していて思ったんですけど、イメージって僕らは見ているじゃないですか、目からどんどん情報が入ってくるという意味では。でも、僕らは普段これをイメージとして捉えていない。ではイメージとして捉えるものって何だろうと考えた時に、僕が最初にイメージとして考えるものは、光学的な装置を通じてスクリーンの上に定着、あるいは、その上にのっかっているもののことなんです。カメラやヴィデオのファインダーをのぞいている時はイメージという印象がないのに、その横につけられたモニターに映った映像を見ている段階で、これはイメージだな、と思った。それはもう自分の目の延長上にないんですね。ここにあるモノになっていて、これがイメージなんですね。 その前の児玉画廊(大阪)で発表した「Camera
Lucida」という作品を今回ドイツで展示してきたんですが、レンズとスクリーンだけがあるというような作品で、再展示していて思ったんですけど、イメージって僕らは見ているじゃないですか、目からどんどん情報が入ってくるという意味では。でも、僕らは普段これをイメージとして捉えていない。ではイメージとして捉えるものって何だろうと考えた時に、僕が最初にイメージとして考えるものは、光学的な装置を通じてスクリーンの上に定着、あるいは、その上にのっかっているもののことなんです。カメラやヴィデオのファインダーをのぞいている時はイメージという印象がないのに、その横につけられたモニターに映った映像を見ている段階で、これはイメージだな、と思った。それはもう自分の目の延長上にないんですね。ここにあるモノになっていて、これがイメージなんですね。
鏡に関していえば、「photo-gene」展の後に坂本(龍一)さんと大徳寺でライヴをして、その時も映像のアイディアについていろいろ考えていたんですけど、どこかで撮影してきた映像をプロジェクションする、みたいなことよりも、もっとシンプルな、原始的な映像を使えないかなと思って、鏡を使ったんです。個展の時に鏡を使っていたのも同じことで、つまり、映像装置なんですよ。しかも「photo-gene」で使っていたのは単なる鏡じゃなくて、パフォーマンス「Voyage」の舞台で床に使っていた鏡なんです。なので擦り傷なんかがたくさんあるんですけど、もしも単なるきれいな鏡だったとしたら、映像がそこで止まらないなあ、と思っていたんですよ。イメージが向こうへ突き抜けてしまって、フレームがフレームとして存在しない。でも、パフォーマンスの痕跡でもある傷のおかげで、イメージが止まるんですよね。
 池田:たしかに高谷さんが制作をされている中で「イメージ」というものは中心的な問題だと思います。では、そのイメージの条件というのは何でしょうか?空の写真ということで言えば、上を見上げているその視覚的情報は、高谷さんの考えるイメージではない。 池田:たしかに高谷さんが制作をされている中で「イメージ」というものは中心的な問題だと思います。では、そのイメージの条件というのは何でしょうか?空の写真ということで言えば、上を見上げているその視覚的情報は、高谷さんの考えるイメージではない。
高谷:見ていること自体はね。僕が感じていることで、共有も出来ない。
池田:それが写真になってイメージになる。そこにはどのような違いがあるのでしょうか。一つにはフレームへの意識、もう一つは支持体への意識ということでしょうか。傷のついた鏡に言及されましたが、傷があり、イメージが歪められることによってこそ、モノとしての支持体の上にイメージが現れている、という事態が意識化される。
高谷:そう、意識化された映像。なおかつ二次元まで次元が一つ落ちていること。自分の通常の感覚よりも一つ次元を落としておいた方が、意識化しやすいんですよ。なのでスクリーンを通した時点で、僕にとってイメージが始まるんだな、という気がしますね。
「LIFE - fluid, invisible, inaudible ...」では記録映像をたくさん使っています。僕が撮影したものでなかったり、地図であったり。例えばあれがきれいな磨りガラスとかにプロジェクションしていたとしても見れなくはないと思うんですよ。ただそうなってきた時にソースが持っている解像度とかがクオリティとして問題になってきてしまう。そういう意味ではあれは、映像としてというより、そこで発生している出来事として受け取ってほしい、という気持ちがあったんです。透明な箱の中で映像が霧に映されることによって、もう一度、出来事になる。それごと受け取ってほしい、という所がありました。
池田:確かに霧の部分は、映像そのものの蒸発を見ているような、そういう意味ではまさに出来事として見えてくるものでした。映像がもつ意味内容が、気体となって消滅していくかのような。
|