八〇年代は八〇年代で、今のぼくらと同い年くらいの作家がいたわけだね、あたりまえだけど。そして、一〇代のぼくらは、そういった作家の作品に、接してきたのでもある。ぼくは八〇年代にデビューした作家の、何人か、当時の活躍も今の活動も、大好きだけど、気になるのは、たくさんしゃべってたくせにさ、たくさんの言葉を書いてたくせに、肝心なところ、さっさと終えちゃった気がする。その速さが上の世代を意識したものだというのは、わかるんだけど、早熟なのは、魅力なんだけど……。
 そうね。それで(自分たちと)同じように顰蹙を買うべきだみたいに、いわれるとさ……。 そうね。それで(自分たちと)同じように顰蹙を買うべきだみたいに、いわれるとさ……。
 対談? 顰蹙対談?(編集部注 対談「『顰蹙』こそ文学」[山田詠美、高橋源一郎]『群像』二〇〇五年一月号、鼎談「顰蹙(文学)の力」[島田雅彦、山田詠美、高橋源一郎]同四月号) 対談? 顰蹙対談?(編集部注 対談「『顰蹙』こそ文学」[山田詠美、高橋源一郎]『群像』二〇〇五年一月号、鼎談「顰蹙(文学)の力」[島田雅彦、山田詠美、高橋源一郎]同四月号)
 たぶんその曲芸のようなことで荒らしていったときに、より上の世代に顰蹙を買ったんだろうね。 たぶんその曲芸のようなことで荒らしていったときに、より上の世代に顰蹙を買ったんだろうね。
うん。
 そのことをふまえて、今、覇気がない、もやしっ子みたいなさ(笑)、作風の人が、みたいなさ。でもぼく、あの言葉を聞いたときに、ある種の安心感、つまりより上の世代に顰蹙を買ったという図式からいうと、もう同じように、もうなってると思ったよ。 そのことをふまえて、今、覇気がない、もやしっ子みたいなさ(笑)、作風の人が、みたいなさ。でもぼく、あの言葉を聞いたときに、ある種の安心感、つまりより上の世代に顰蹙を買ったという図式からいうと、もう同じように、もうなってると思ったよ。
 ああ、もう買ってるんだ(笑)。「最近の子は顰蹙を買ってない」っていう顰蹙を買ってるわけだ(笑)。 ああ、もう買ってるんだ(笑)。「最近の子は顰蹙を買ってない」っていう顰蹙を買ってるわけだ(笑)。
ほんとだね。
 なんか逆説的に……、逆説じゃないな。なんか、とにかく、ある意味では、それで、じゃいいんじゃないの、と思う。 なんか逆説的に……、逆説じゃないな。なんか、とにかく、ある意味では、それで、じゃいいんじゃないの、と思う。
 そう、それはわたしも思ったし、そういう書き方をしたいなあっていうのは、そういうね、反抗するっていうことで顰蹙を買うっていうのはね、前の、だいぶ前のことだから。 そう、それはわたしも思ったし、そういう書き方をしたいなあっていうのは、そういうね、反抗するっていうことで顰蹙を買うっていうのはね、前の、だいぶ前のことだから。
ああ。
 そうだよね。 そうだよね。
 わたしの「ああ、そういうんだったら、それは、そうかも」みたいなのをね、きっと腹が立つ人はいっぱいいるだろうなって思って(笑)。 わたしの「ああ、そういうんだったら、それは、そうかも」みたいなのをね、きっと腹が立つ人はいっぱいいるだろうなって思って(笑)。
うんうん。
 わたし逆に、そういうことを言ったらムカつかれるんじゃないかな、と思いながら言ってるところもある(笑)。ひねくれてるのかな。 わたし逆に、そういうことを言ったらムカつかれるんじゃないかな、と思いながら言ってるところもある(笑)。ひねくれてるのかな。
ああ、それはすごくよくわかる。うん。
 うん。 うん。
早熟なお兄さんとかお姉さんがたくさんしゃべって、柴崎さんが「それはそうですね」って一言で片づける(笑)。
 やだろうな、みたいなね(笑)。 やだろうな、みたいなね(笑)。
でも効率がいいのは、こっちなんだよ。嘘じゃないし、皮肉でいうのでもないでしょう。
 だってほんとにそう思うしなあ。「そういう考えもあんねや」、みたいなね(笑)。 だってほんとにそう思うしなあ。「そういう考えもあんねや」、みたいなね(笑)。
 でもね、顰蹙を買うべきだっていうのが、その時代にそういうふうに出てきた人の、本音と自負と苛立ちみたいなものとして……、つまり逆のポジションに自分がいたらって考えると、それはそれですごくわかるんだよね。 でもね、顰蹙を買うべきだっていうのが、その時代にそういうふうに出てきた人の、本音と自負と苛立ちみたいなものとして……、つまり逆のポジションに自分がいたらって考えると、それはそれですごくわかるんだよね。
 うん。 うん。
 だから真っ当に現役感があるじゃないですか。八〇歳くらいまで、みんなこう、下の世代に対して、すごい負けまいっていうかね。自分が現役であるっていう感じを、捨ててないし、現役であるっていう。それはもう、顰蹙を買うべきだっていう発言からも、「あ、現役だ!」みたいなさ。 だから真っ当に現役感があるじゃないですか。八〇歳くらいまで、みんなこう、下の世代に対して、すごい負けまいっていうかね。自分が現役であるっていう感じを、捨ててないし、現役であるっていう。それはもう、顰蹙を買うべきだっていう発言からも、「あ、現役だ!」みたいなさ。
 うん、たしかに。 うん、たしかに。
それに応接していく、応じていく姿勢っていうのが、ぼくらの場合、「そうですね」っていう返し方(笑)。
 うん、ほんとそう。だって「えらいなあ」みたいな感じなんだよ。嫌味じゃなくて。 うん、ほんとそう。だって「えらいなあ」みたいな感じなんだよ。嫌味じゃなくて。
うん。そうなんだよ、それはよくわかるんだよ。でも、それは柴崎さんの、ほんと、皮肉ではないところ、本当なんだってところに、かえって、不穏さが宿るというかね。
 作品にもそういう感じはあるよね。なんか不穏さがある。 作品にもそういう感じはあるよね。なんか不穏さがある。
 うん、そう、不穏な感じはずっと書きたいと思ってて。あ、けど、そういう例でわかりやすいとこでいえば、『きょうのできごと』で、二人どうでもいい人がいて、《緑》と《黒》って呼んでて、本当にどうでもいいっていう(笑)。 うん、そう、不穏な感じはずっと書きたいと思ってて。あ、けど、そういう例でわかりやすいとこでいえば、『きょうのできごと』で、二人どうでもいい人がいて、《緑》と《黒》って呼んでて、本当にどうでもいいっていう(笑)。
 すごい変に髪切られちゃうんだよな、たしか。 すごい変に髪切られちゃうんだよな、たしか。
 そうそう。 そうそう。
一方では男前と書かれる登場人物もいて。
 そうそう、男前の子には、なんかねえ、優しく髪切ってんのよねえ。《黒》と《緑》って、どうでもいい、本当にどうでもいいんですよ、あの語ってる子にとっては。 そうそう、男前の子には、なんかねえ、優しく髪切ってんのよねえ。《黒》と《緑》って、どうでもいい、本当にどうでもいいんですよ、あの語ってる子にとっては。
 話者じゃなくて、作者もね(笑)。 話者じゃなくて、作者もね(笑)。
 作者は、まあもうちょっと愛情があるけど(笑)。まあ、あの女の子にしてみれば、たぶん、次の日になっても区別ついてなくて、「え、そんな人いたっけ?」みたいな感じで、どうでもいい(笑)。 作者は、まあもうちょっと愛情があるけど(笑)。まあ、あの女の子にしてみれば、たぶん、次の日になっても区別ついてなくて、「え、そんな人いたっけ?」みたいな感じで、どうでもいい(笑)。
 でもね、それがどうでもいいっていう排他的なふうに見えない仕組みがあって、つまりあの語り手の女の子、すごい酔ってんだよね。 でもね、それがどうでもいいっていう排他的なふうに見えない仕組みがあって、つまりあの語り手の女の子、すごい酔ってんだよね。
 そうそう。 そうそう。
 だから読む側は、「これは酔ってるせいで、面食いな面が特別に出てるだけかな?」っていう留保があるんだよ。 だから読む側は、「これは酔ってるせいで、面食いな面が特別に出てるだけかな?」っていう留保があるんだよ。
やっぱ語り手、ちょっとおかしいよね。
 おかしい(笑)。 おかしい(笑)。
 柴崎さんの小説のなかの、このことは語って、このことは語らないっていう、恣意的に選ばれて目に入ってるものって、絶妙によくてさ。田舎の民宿の事務室へ行ったら、みょうに重そうな灰皿がある、みたいな(笑)。 柴崎さんの小説のなかの、このことは語って、このことは語らないっていう、恣意的に選ばれて目に入ってるものって、絶妙によくてさ。田舎の民宿の事務室へ行ったら、みょうに重そうな灰皿がある、みたいな(笑)。
 ああ。 ああ。
 重そうな灰皿のことは、ほかの作家も書くかもしんないんだけど、その作家はきっと、もっと他のものも書いちゃうんだけど、柴崎さんは、重そうな灰皿とあと二点ぐらい(笑)。 重そうな灰皿のことは、ほかの作家も書くかもしんないんだけど、その作家はきっと、もっと他のものも書いちゃうんだけど、柴崎さんは、重そうな灰皿とあと二点ぐらい(笑)。
 (笑)。 (笑)。
 それでいながら、ちゃんと事務室になる、みたいなね。 それでいながら、ちゃんと事務室になる、みたいなね。
うんうん。
 その選んであるものがまず正解だし、書かなくていいものも正解、と思わせるような、感じっていうのは、舌を巻くぐらい、あるよ。 その選んであるものがまず正解だし、書かなくていいものも正解、と思わせるような、感じっていうのは、舌を巻くぐらい、あるよ。
最初からそれが意図的だっていう気がするのは、題名が色の名前だったりする。
 だから、Amazonのさあ、読者レビューで柴崎作品に《で、だから?》って書いてる人がいてさ。つまり、読んだ後で、「で、だから?」っていう気にさせる。《で、だから?》っていわれたのは、成功してる(笑)。 だから、Amazonのさあ、読者レビューで柴崎作品に《で、だから?》って書いてる人がいてさ。つまり、読んだ後で、「で、だから?」っていう気にさせる。《で、だから?》っていわれたのは、成功してる(笑)。
 そう、成功してるんだよね(笑)。それでいいの。 そう、成功してるんだよね(笑)。それでいいの。
 うん。ある人のある角度から見たときには、《で、だから?》っていうものに見えてないと、別の角度から見た人にすごくかがやくものにならないっていうかさ。でもいちおう、体(てい)として、『フルタイムライフ』でも、一〇ケ月とか、『ER』みたいな、最後の方で失恋した主人公が新たな恋を見つけそうみたいな、最低限の体(てい)はあるんだよね。 うん。ある人のある角度から見たときには、《で、だから?》っていうものに見えてないと、別の角度から見た人にすごくかがやくものにならないっていうかさ。でもいちおう、体(てい)として、『フルタイムライフ』でも、一〇ケ月とか、『ER』みたいな、最後の方で失恋した主人公が新たな恋を見つけそうみたいな、最低限の体(てい)はあるんだよね。
 そう、ある。いちおう(笑)。 そう、ある。いちおう(笑)。
 そうすると、女性誌に載ったときに《傷ついたOLの》とか、《仕事に恋にがんばる》とか書かれる。 そうすると、女性誌に載ったときに《傷ついたOLの》とか、《仕事に恋にがんばる》とか書かれる。
 《新しい恋を見つけるまでの一〇ケ月》みたいな感じでね(笑)。 《新しい恋を見つけるまでの一〇ケ月》みたいな感じでね(笑)。
 一〇行でいうならこんな粗筋、みたいなところに応え得る、最低限の体(てい)は用意してある。それがないと、《で、だから?》が増える。 一〇行でいうならこんな粗筋、みたいなところに応え得る、最低限の体(てい)は用意してある。それがないと、《で、だから?》が増える。
なるほど。
 ほんとは、だから今は、粗筋が書けない話を書きたい。 ほんとは、だから今は、粗筋が書けない話を書きたい。
 そう! それを書きたいんじゃないかって思ってた。最後に、新たな恋を見つけそうになるのは、邪魔じゃないし、あってもいいとは思うんだけど、なかったらもっとすごい。ぼくもそうなんだよ。何か……。なんというか、現状、値段がついて本が流通する仕組みのなかで、体(てい)があってもしょうがないみたいなさ(笑)。つまり、体(てい)がなくても、ない瞬間に、正しい言葉でいってくれる人がほんとに現れるかっていうノノ。あ、でも、この「山根と六郎」は、かなり体(てい)がない(笑)。 そう! それを書きたいんじゃないかって思ってた。最後に、新たな恋を見つけそうになるのは、邪魔じゃないし、あってもいいとは思うんだけど、なかったらもっとすごい。ぼくもそうなんだよ。何か……。なんというか、現状、値段がついて本が流通する仕組みのなかで、体(てい)があってもしょうがないみたいなさ(笑)。つまり、体(てい)がなくても、ない瞬間に、正しい言葉でいってくれる人がほんとに現れるかっていうノノ。あ、でも、この「山根と六郎」は、かなり体(てい)がない(笑)。
 うんうん! なかった。この話、すごいよかった。おもしろかった。 うんうん! なかった。この話、すごいよかった。おもしろかった。
 「じゃあね」っていう言葉は、子供も「じゃあね」っていうし、高校生も「じゃあね」っていうし、すごくこわい、肩がぶつかったら殴られそうな人も、「じゃあなー」みたいに、みんな「じゃあねー」とか「じゃあなー」とかいうんだっていう話なんですよ。 「じゃあね」っていう言葉は、子供も「じゃあね」っていうし、高校生も「じゃあね」っていうし、すごくこわい、肩がぶつかったら殴られそうな人も、「じゃあなー」みたいに、みんな「じゃあねー」とか「じゃあなー」とかいうんだっていう話なんですよ。
要約だと、まったくわかんないけど、それはいいね(笑)。
 これ粗筋書けないよね。 これ粗筋書けないよね。
 うん、書けない。粗筋は、きっと、本編と変わらない長さ(笑)。 うん、書けない。粗筋は、きっと、本編と変わらない長さ(笑)。
2005/07/28 大阪にて
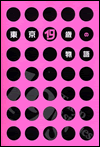 ##下記応募は締め切りました## ##下記応募は締め切りました##
★読者プレゼント★
本文中にも話題にあがりました『東京 19歳の物語』を、長嶋有氏と柴崎友香氏からのご提案により、
おふたりのサイン入りで1名様にプレゼントいたします。
ご希望の方は必要事項を記入の上、メールにてお申し込みください。
[応募締めきり]
9月30日 |
[必要事項]
お名前
ご住所
電話番号
メールアドレス
対談記事のご感想
log osaka web magazineをお知りになった媒体
|
※お送りいただいた個人情報は、プレゼントの発送に関するご連絡以外で使用することはありません。
抽選の結果は、厳正なる抽選の上、当選者への発送をもってかえさせていただきます。 |
|

