 |
 |
 |
 |
log編集室:デザインする際に江村さんが意識されていること、力を入れておられることはどのようなことなのでしょうか?
江村:キュピキュピや私の個人作品の上でグラフィックデザインをする時はともかく、デザイナーとして「誰かの思い」をかたちにする場合は、まずその対象物を楽しむところから始まります。魅力がわからないとデザインできないんです。どういう状況でデザインをするにしても対象物に対するきちんとした認識と愛着と「楽しい!」という視点がないと、デザイナーがいる必要がないと思うんです。実際のところ、多くのデザイナー達は沢山の仕事量を抱えていて、一つ一つの内容を楽しいと感じるのは難しいのかもしれません。でも頑張ってやるべきだと考えています。
もう一つは「送り手はこういう風に受け手に伝えたいだろうな」ということを常に意識して作ることです。Breaker
Projectの場合は、雨森さんや各アーティストが求めているものや質が明確で、僕もそれが面白いと思う。おまけに僕はそんなに仕事を抱えていないから時間も充分にかけられる(笑)。それでしっかりとしたデザインができているのだと思います。
突き詰めると「伝えたいものが面白いかどうか、大切かそうでないか」、デザインをするのに重要なのはそれだけかも知れません。
雨森:それは自分にとって、ですか?
江村:自分にとって、と同時にみんなにとっても、なのかな。本当にみんなが素晴らしい感覚になるんじゃないかなっていうものごとに対しては、何としても伝えたいって思います。そう思うことによって良い緊張感が持てるし、楽しんでやれてしまう。
広告を作っていた20代の頃は「これはおかしいな」と思いながらデザインすることも多かったんです。すごくイヤなことを人や街にしているかも・・・でも仕事だから・・・という感覚。それがだんだん「僕は広告の仕事に向いてないのかな」と思うようになって。そのうち「僕がしたいな」と思うことはした方がいいし、「僕がしたくないな」と思っていることはしてはいけないんだろうな、と素直に考えるようになりました。広告であろうがなかろうが、疑問を持ってデザインしたモノが良いモノになるわけがないし、そんな良くないモノが世の中に出てしまうとさらにもっと良くない。 |
|
 |
 |
log:デザイナーには「人々は、ものごとをどう見ているのか」を的確に捉えられる「常識」や「良識」という感覚が必須です。それを踏まえつつそこからどうずらすか、どこまでずらすか、という作業がデザインの醍醐味ではないですか?
江村:そういうやり方もありますね。
松本:その“ずらし方”の匙かげんについて具体的に伺いたいのですが、「ここまでずらしても大丈夫、ここまでずらすと受け手側が分からなくなっちゃう」と判断する基準はどこにあるのですか?敢えてそのギリギリを狙って受け手の感受性を引き上げたり、引き出したりすることで「ああ、こういうのもアリだな〜」という感覚にさせることもデザイナーの仕事の範囲なのかな、と考えたりします。
江村:受け手を特定のターゲットに絞ることができれば、ピンポイントでそこを狙えるから効果的なやり方ではあるんでしょうね。だけど、今僕が作ったり考えたりしているのは「デザインでびっくりさせたくない」ということです。「この中身がこんなに面白いから、それを理解してびっくりして」というスタンス。表面の面白さというよりは中味の面白さを引き立たせるためのデザイン。だからそういう意味では、「そこまでずらすと、受け手がわからないかも」という仕事の仕方はまずしません。「送り手はこういう風に伝えたいんだろうな」というのをそのままに伝えたい。それは僕が、その人や、その人がやろうとしていることが好きだったり、面白いと思っていたり、敬意を払っているからなのでしょう。だから「ストーン!と、まっすぐ伝われ」という気がする。そのために余計なことはしたくないですね。 |
|
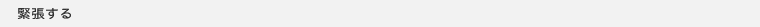 |
log: ある用途や、ある出来事をどのようにすれば伝えることができるのか?どうしたら手にとってもらえるのか?そこを担うのもデザイナーの役割ですよね。
江村:そうですね。仮に中味がすごく面白くても、それに手を伸ばしてもらえなかったら0点になってしまいます。その情報が重要であればあるほどその0点は痛い。デザイナーに限らず作り手は、その辺りの緊張感や責任感を強く感じた方がいいですね、いい意味で。 |
|
 |
log:デザイナーにとって(どんな職業にとっても)キャリアを積むことは大切です。グラフィックの処理やフォントの選択や色みの問題など、キャリアを積むごとにボキャブラリーがストックされていきます。そして、ある程度の引き出しが一旦できてしまえば例えば「ああすればロック風、ああすればフレンチポップ風」というように作ることが容易にできるようになっていきます。逆に組み合わせ次第では、それのどれでもないイメージやどれでもないテイストも作れるはずです。デザイン次第で、全体のイメージがすごくニコニコしていたりもするし、暴力性を帯びていたりもする。その辺り、江村さんはどのように作業されているのですか?
江村:流行りのナントカ風からは明確に逃げようとしています。あまり流行を知らないというのもあるのですが(笑)。「こうすればアレ風」といった感覚からはモノは作っていません。
僕は友人とデザイン事務所を作って、それを一旦辞めてグラフィックから離れた時期があって、その後もう一度グラフィックに戻ってきたんです。デザイン事務所の頃からコンピュータでデザインする時代には入っていたんですが、戻ってきた頃にはソフトも進化していてフォントもどんどん増えていく、海外からも新しいフォントが入ってきてファッション系等にどんどん使われている、でも美しいフォントは高くてなかなか手に入らないし、きりがない、そんな状況でした。ある時、この流れを追っかけることに疑問を感じたのかな。新しいフォントに対する意識が少し遠のいた、というか逃げようとしたというか。邪魔臭くなったというか(笑)。
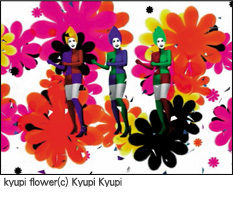 その頃からキュピキュピで映像作品を作り出していました。何回見ても何十年経って見ても面白い映像作品を作ろうと思っていました。とりあえず今っぽいものは全部排除していきました、作品の中で。だからフォントもオーソドックスなモノしか使わなかった。それで充分面白いことができると思いました。そんな流れもあってか、最近はコンピュータを買うと初めから入っているようなフォントしかほとんど使わなくなっています。一般に使われているものだけで組み方や雰囲気作りを工夫して新鮮なイメージを作る方がいいと思ったんですね。それと、今は紙媒体と同じものをwebでも見るので両方で同じように見せるためにも、あまりデリケートなフォントは使いにくいかな、とも考えています。 その頃からキュピキュピで映像作品を作り出していました。何回見ても何十年経って見ても面白い映像作品を作ろうと思っていました。とりあえず今っぽいものは全部排除していきました、作品の中で。だからフォントもオーソドックスなモノしか使わなかった。それで充分面白いことができると思いました。そんな流れもあってか、最近はコンピュータを買うと初めから入っているようなフォントしかほとんど使わなくなっています。一般に使われているものだけで組み方や雰囲気作りを工夫して新鮮なイメージを作る方がいいと思ったんですね。それと、今は紙媒体と同じものをwebでも見るので両方で同じように見せるためにも、あまりデリケートなフォントは使いにくいかな、とも考えています。
log:紙媒体とwebとの連動ですね。
江村:そうです。Webでは紙面独特の繊細な線や色や質感などは伝わらないですよね。それがダメという意味ではなくて、メディアの個性と捉えています。
最近フォントの使い方がどんどんシンプルになってきています。Breaker Projectのパンフレットも日・英各1種類でレギュラーとボールドだけしか使っていない。有名なネヴィル・ブロディっていうデザイナーも、ある雑誌1冊に1つのフォントしか使ってなかったりする。1つのフォントのボールドからライトまで、それだけ。それでイメージをいっぱい作って雑誌1冊作っちゃう。かなりの自信と実力がないとできないですけれど、要はやり方次第です。
文字って形だけでイメージが限定出来ない場合もあるんです。明朝とゴシックでもどちらが繊細とか強いとかは実は決めつけられない。流行っているから使うというのもイヤですし、昔のものを昔のまま使うというのもイヤなんです。例えば、細〜いフォントを大きく使うとデリケートでなおかつ強くなるということもある。回転したり・立体化したり・透明にしたりすることで、いくらでもイメージを拡げることだってできる。普通に皆が使えるフォントで新鮮なイメージができるとしたら、皆もそれが使えたりするわけだから、それは便利じゃないかなと思います。

例外的に「オー!マイキー」のように微妙な時代感覚を面白みとして使った作品の場合はちょっと違うことをしています。ソープオペラのような懐かしい感覚の中で、出て来る登場人物が全てマネキンっていうのが大切だった。具体的な時代性を感じられる物だとか、わかりやすいイメージを使うことで、作品自体の面白さを伝わり易くするのが狙いだったんです。そうそう、今夏にはテレビでは放送禁止になったものだけを集めて8本目のDVDを発売するんです。題して「オー!マイキー
ハードコア」(笑)。それのためにハーレーダビットソンのようなロゴを作ったんです、メタリックで羽がついてたりして(笑)。あ、話が違いますね(笑)。
|
|
 |
松本:現状としては、コマーシャルの領域でデザイナーとして生きておられる方の立場ってどういう状況なのですか?例えば、クライアントの要望に対してついていけなかったり、「おかしいな」と思った時に、デザイナーができることってどんなことなのでしょうか?
江村:デザイナーもいろいろで、外部のデザイナーもいれば、企業内デザイナーもいますね。企業内デザイナーなら、立場によっては発言力もあって良からぬ方向に話が進み出した時には上に対して意見できる。とても力のある外部デザイナーはもっと強くクライアントに発言できるかもしれない。でも大多数の外部デザイナーはクライアントに意見できない。仕事を失うということになりかねないから。ここが問題。クライアントはもっとデザイナーなど外部の人の話を聞かないといけないし、デザイナーももっと真面目に考えを伝えるべきです、いろいろと勉強しないといけないですが。一緒に作っているという感覚を持つことで、クライアントもデザイナーも街も育つと思うんです。 |
|
 |
log:[log]は、地域に向けて「文化」という切り口から情報発信しているweb magazineです。そこでの一連の動きは、コマーシャルとは少し違った感覚や価値観が働いています。例えばアート系のNPOや行政の文化集客施設などのオルタナティブ[註:オルタナティブ・・・もう一つの、既存に代わる新しい、選択肢、多目的の、などと辞書にはある。ここでは、コマーシャルの論理には当てはまらない、多様な価値観を持った、という意味で使用している。]スペースで行われる催しを取り扱う際、いわゆるコマーシャルとは違った視点が必要だったり、情報発信の力点が違います。その理由の一つには、その場に訪れる方々がコマーシャルにはない体験を求めてこられる、ということが挙げられます。
一方で、行政と仕事をしているとデザインというのはぜいたくなもの、もしくはファッションと受け止められるケースが多々あります。[log]の動きと平行して [C/P地域文化活性のための情報誌
](1999〜2004)というフリーペーパーを行政と作っていた時のことですが、当初行政のデザインに対する考え方は「デザインにかける労力は不必要である、ましてお金を投価するのなんてとんでもない・・・」という調子でした。しかし本当は、デザインがなされていないものなんて世の中にないんです!
他にも例えば、行政が作る老人や子ども向けの予防接種を訴える広報物にしても、全くメッセージがこちらに届いてこない。文字の大きさ、情報の整理の仕方を少しだけ変えただけでも全然印象が変わって来るのにな、と痛感します。他にもコピーに対する感覚。「みんなの街、わたしたちの街」。死語化している言葉=届かない言葉を延々と再使用している。ターゲットが大衆になった途端、一挙にデザインのディレクションが良からぬ方向に行ってしまう。送り手(行政)のデザインに対する考え方がそうだから、デザインにお金をかけない、優秀なデザイナーが集まらない、受け手にも届かない、効果が出ないからさらにお金がかけられない、という悪循環に陥ります。
しかし、楽観的な言い方をするとデザイナーにとっては介入できる大きなマーケットが広がっているということです。特にデザインを勉強していたり職業としてのデザイナーを目指している若い力がオルタナティブ(行政を含めた)の領域でデザインに挑戦してキャリアを積むということも面白い動きなのではないでしょうか。
江村:同感です。チームを組んで「この街のデザインは全部俺らがやる!」といったチャレンジがあってもいいですね。コマーシャルでのデザインに負けないぐらいのテンションを持って作れるかどうかが問題ですが。予算が無くても知恵を絞ることで飛躍的に良いものができると思うんです。実際やってみると面白いはず、デザイン的な変化・結果が分かりやすいでしょうから。行政が理解して少しでもマネーフローを作って積極的に人が集まりやすい環境を整えるべきですね。そこで投資されるお金はとても意味があると思います。
雨森:行政の作る印刷物が良くなれば、長い目で見ると街全体の雰囲気もかなり変わるんじゃないでしょうか。 |
|
 |
江村:若い人たちにもそういうことを任せていい、そう思う反面、若い人達が作っているフライヤー等を見ても面白いのが少ないのも現実です。好みもあるのでしょうがつまらない。何でなんだろうな、と思います。
log:基本的なところが押さえられていない、ということが理由の一つかもしれません。デザインをする前に「情報を探す、見つける、整理する」という動きが必ずあるんですが、情報って探せば探すほどミクロに膨大にあると思うんです。デザイナーが情報を得る時に、起承転結の構成や5w1h(いつ、だれが、どこで、なにを、なぜ、どのように)というベーシックな情報が押さえられないとツールとして低下してしまう部分はあります。そこの基本的なことを押さえただけで、それに少し手を加えれば一段とよくなるかもしれないですね。
加えて現状のグラフィックデザインという領域でデザイナーが動ける範囲が限られているというのも背景にあるんじゃないでしょうか。仕事ではあまり無茶なことはできないからデザインの領域までが狭められてしまう。そんな環境でしかキャリアが積めないとすれば、彼ら自身もデザインの幅が持てなくなるのも当然です。もしそうだとすれば、すごくもったいない気がします。
江村:そうですね。今も同じだと思うんですが、僕も若い頃に「納得いくまで調べろ!」という教育を受けました。広告の中でコピー全盛期の頃、半年間ほどコピー塾に通っていたことがあって。僕はアートディレクターになるつもりだったから「コピーのこともわかってないといけないな」と思って通っていたんです。コピーって実は、情報がないと何もできない仕事の典型ですよね。勉強になりました。
情報を吟味して取捨選択をするスキルを磨くためには、普段から「意識して見る・きょろきょろする」ということがすごく大切です。身近にあるデザインされたものに「これはいい、これはよくない」とつっこみをいれながら生活する感覚。すごい情報量の世の中だし、媒体も紙からwebまで幅広いし、決まったルールもないから簡単には自分のものにはできないでしょうが、まず見ること。おまけにそういう混沌の中で、いびつに映ったものや反則技が一気に宝石に見える時もある。整理ってむつかしい。
log:同感です。整理の仕方次第で読みにくくもなるし、読みやすくもなる。実は、情報の整理整頓がデザインの仕事の中で、かなりのウェイトを占めているのでないかと思います。 |
|
 |
江村:大学の授業で「自分のイラストを使って広告を作る」という課題を出した時にも、「伝えるにはどうしたらいいか?」ということに生徒はあまり気を配らないんですよ。書いてあったら伝わると思っているみたいで。
雨森:実際に自分が困った経験がないと、そういうことには気づかないかもしれないですね。
江村:そう、受け手側に対する配慮がないってことですね。受け手側に立って考えてみたことがない。
松本:本当に伝えるべきことが見つけられないから、ピントを合わせられず、全体的にぼやけちゃうのかもしれないですね。見つかれば、モチベーションも上がるし、受け手側の輪郭も作りながら見えてくるのでは。
log:そこに自ずと「伝える」という責任が生まれる。
江村:緊張感も生まれる。
最初にも言ったけれど、やっぱり「僕は、私は、それを伝えたいかどうか?」ということと「面白がる」という話になるんです。本気で伝えたいと思っているなら、例えばレイアウトを組む際も「はい、組めました」で終わりにはならなくて、次の段階の「もっと、こうしたほうが良い」が見えてくるはず。デザインする対象物を面白がれて、それを多くの人にも面白く伝えようとすること。その対象物が今までにない感覚のものなら、今までにない感覚のものとして伝わるべきだと思うから、新しいデザインの方法があるかもしれない、という考え方の流れ。新鮮さを独りよがりで無理矢理ひっつけるのではなく、対象物を新鮮に面白がった時にでてくる「うわ、こんなん出て来たわ!」という自分に対しての驚きも含んだモノが出来ると、皆が楽しくなれると思うんです。
グラフィックデザイナー皆がこんな考え方・動き方をしたら社会は困るかも知れないけど、僕ぐらいはこういうやり方でやってもいいんじゃないかな、と思っています(笑)。
log、雨森、松本:ありがとうございました。[了] |
|
| |
 |
 |
 |
 |

