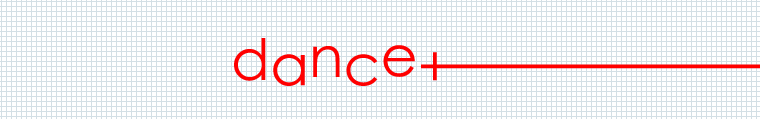
| 日々是ダンス。踊る心と体から無節操に→をのばした読み物 |
|
|
|
28 京都の暑い夏2007ドキュメント Vol.3
ビデオサロンレポート(1)映像とダンス —<ヴィデオラマ>と<ビデオサロン>を振り返って—
by メガネ [dance+]
■ なぜダンスを映像で見るのか
映像で見るダンスはつまらない。
これは、ダンスの映像を鑑賞したことがある者なら、誰もが抱いたことのある感想ではないだろうか。
けれども今後、映像の中のダンスが舞台舞踊の受容や流通におよぼしてゆく影響は、ポジティブに見積もっておきたい。そう思うのは、昨今の生活環境に埋め込まれてゆく大小のモニターやコンテンツと呼ばれる映像の増加にもとづいての楽観では決してない。現実には、80年代に欧米で注目されたビデオダンス*に対するテレビの制作枠は減ってゆく傾向にあると聞くし、舞台舞踊の性格上、ダンスがコンテンツ産業とやすやすと結びつくとは考えにくい。結びついたら面白いけれど、映画の黎明期や50年代のハリウッドとは状況も異なるのだ。
*ビデオダンスは、映像作品として制作されたダンス。たとえばこんなの>>>
では、なぜダンスに関わる上で、映像にこだわるのか。
ひとつには単純に、映像の中のダンスは、その場で消え去ってしまったダンスや“今ここ”では体験できないダンスについて知るための貴重な手がかりだからだ。現にビデオダンスや舞台舞踊の記録は、80年代以降の欧米のコンテンポラリー・ダンスと、さらにその背景にある歴史の受容の一端を担って来た。もちろん、そういった舞台舞踊への関心とセットで受けとめられてきたことが、先の「つまらなさ」の背後ではたらいている、現実とその模造、オリジナル作品とそのコピーといった序列意識をかたちづくってもいるのだろう。けれども一方で、映像を用いたダンス作品やビデオダンス作品に目を向けてみれば、そういったダンスと映像の固定した関係を揺るがすような試みも少なくない。価値判断の拠り所となってきた舞踊史が失効したと言われる今こそ、横並びに陳列される個人の表現を自分なりのやり方で楽しむ軸を得る手がかりとして、自らの身体や言葉とともに、映像の可能性が積極的に捉えられてもいいのではないか。
こんな思いもあって「京都の暑い夏」の<ビデオサロン>に関わって2回目。鑑賞者として、企画者として、困難を感じもしたが、終えてみて、課題や今後の展開の可能性もはっきりしてきたように思う。その際少なからぬ示唆を与えてくれたもう一つの「暑い夏」関連イベント、<ヴィデオラマ>と併せて、筆者が担当したビデオサロンの1日目を振り返ってみたい。
■ ダンスをめぐる問題系と映像の結びつき <ヴィデオラマ>
ポンピドゥー・センターと関西日仏学館の協力により実現したこの催しは、大枠では、フランスのダンス表現の尖ったところを紹介するという体裁をとっている。けれどもそれは、地域を便宜的なくくりとし、その中で評価の高い表現をただ並べたものではなかった。上映された5作品は、それぞれが興味深い映像の中のダンスの例であるにとどまらず、全体として一つのヴィジョンを示していたからだ。それは、プログラムを組んだエマニュエル・ユインの創作上の関心とおぼしき知覚に関する実験なり、彼女が自国で巻き込まれていると説明された“ノンダンスnon danse”をめぐる議論なりをめぐっている。このように、<ヴィデオラマ>は、アーティストのヴィジョンや創作背景への理解を促す企画だが、何よりエキサイティングなことに、こういったヴィジョンが映像の実験と結びついた作品を含んでいた。映像とダンスについて考えるためにも、どのような主題がどんな映像と関わっているかに焦点をあてて振り返ってみたい。
■ ここにはないダンス −面白いことはスクリーンの裏で起こっている?--
まずは第2部の冒頭に上映された『物質プロジェクト』から見ていきたい。ユインの師にあたるオディル・デュボックと造形作家のマリー=ジョゼ・ピエとの共同作業で、舞台上におかれた造形美術を利用し、ダンサーがその物質性と取り組んだ作品の記録だ。当日配布資料には、「それら(舞台美術)とのコンタクトで、ダンサーたちは、私が求めようとしていたダンスのクオリティを見いだした」というデュボックの発言が引かれている。
こういった舞台上のダンスの実験成果は、どのように映像化され得るのか。確かにその工夫は、客席では実現されないアングルや至近距離から撮影された個々のカットに見てとることができる。それでも鑑賞してみて、この実験の主眼である質感がどんなものだったのかつかみとるのは難しいという印象を受けた。まず映像は、引きと寄り、上方からの俯瞰などを織り交ぜて、舞台上に散在し同時進行するコレオグラフィーの再構成を試みる。なので、上演時には作品としてのまとまりや秩序を備えたダンスが存在していたことになり、見る者の意識は常に、この消え去ってしまった全体に方向づけられる。けれども映像が切り取るのは、対象との距離や枠付けの限定されたその断片となる。また、ダンスの質は、そのまるごとを体験する中で感じとることができるものだが、その再現は、機械の目によって制約を受けた視覚を手がかりに行われる。このとき、あるべきダンスはスクリーンの背後にあり、画面上にはその不完全な像が限定されたやり方で映し出されている。こういった構造は、大部分の記録映像を見る体験を枠づけていると思われる。
これに対してプログラムには、スクリーンの後ろにダンスの全き現れが想定されていない作品が含まれていた。その中で面白かったのは、単に上演空間に踊りが存在しない、ノンダンスの記録映像ではない。スクリーンの中でダンスをめぐる実験が展開される、ビデオダンスの試みだ。映像を最終的なアウトプットと定めて制作されるビデオダンスにおいて、ダンスはスクリーン上で組み合わせられることを目的に撮影されている。なので、見る者のまなざしは映像の進行とともにあるダンスに導かれ、画面上にとどまる。ところがユインが選んだ中には、その画面の中にさえ、ダンスが完全に姿を現さないビデオダンスが含まれていた。
■ どこにもないダンス --スクリーンの裏にも中にもダンスはない?--
ユイン自身の作品『偉大なる命/エピソード1』では、ダンスの映像を見るという心構えは終始裏切られる。始まってしばらく、劇場内の客席や舞台や道具など、動くものの全くないカットが続いた後、やっとのことで登場した2人のダンサーの身体や動きも部分的。さらにそこには、どこかよそから聞こえてくるような音楽やテクストがぶつぶつと割り込む。あらかじめ部分でしかない断片が、互いになじみのないやり方で隣りあわせている。ダンスとの絡みで考えれば、これらはダンスそのものというより、ダンスの体験を枠づけてもいる要素を分解したもののようだが、その組み合わせでスクリーン上に姿を現すものは何なのだろう。作者によれば、この作品では「映画の手法」を用いて、「視覚と聴覚を結びつけているステレオタイプを壊す」ことが目的とされているらしい。有機的な部分の組み合わせの総体というダンスや身体に対する通念を、映像によって問い直そうというのだろう。
ユインのこういった実験への関心は、おそらくこの作品だけに限られたものではない。デュボックからの流れで見ると、ダンスそのものに備わる性質から質を感じる知覚へと焦点はシフトしているが、ダンスの未だ知られていない質やあり方を探し求める点で共通している。このとき映像というツールを手にしたことで、ダンスそのものではなくその知覚される内容を、操作や組み合わせのできる素材へと加工することが試みられたのではないだろうか。なので全体にダンサー不在のカットが多く、映しだされる動きや身体も断片化されていることが多いが、それはユインがこの作品で、それらをダンスの体験において視覚に移り込む対象のうちの一つと扱ったからだろう。この作品がフランスで非ダンスと受けとめられたのはそのせいかもしれないが、この作品の「エピソード0」ないしは「2」は、ノンダンスではなく、未知のダンスをめぐる実験となるはずだ。
このような自らの関心にねざす試みの延長に、ダンスの不在をめぐる議論に「巻き込まれ」ることになったユインと好対照をなすのが、狙いすましたノンダンス作品、『100%ポリエステル』のクリスチャン・リゾだ。この作品はすごかった。映像の現在時に体験の焦点をあてている点で『偉大なる命/エピソード1』と共通しながら、ダンスの不在という主題を映像で真っ向から扱っている。映し出されるのは、中央に糸でつり下げられた2枚のシャツ。互いの身頃に袖をまわし、踊る2人の抜け殻のようなポーズでゆっくり旋回する。このようなやり方でダンスの不在を見る者につきつけているにもかかわらず、見る者はそこにないダンスを探し求めはしない。洗練された視覚像であると同時に手触りを感じさせるざらざらしたセピア色の画面の中で、圧倒的な存在感を備えたシャツ、というよりそこにあったかもしれないダンスの不在が、見る者の視線を釘付けにするからだ。味わうべき質は、終始映像を見る現在時にある。この不在の現れは、“ある”と“ない”との表裏一体にもとづくパラドクスへと見る者を誘うが、その謎を単に言葉遊びではなく魅力的なものにしているのは、この“ない”ということの確かな存在感だ。この点で、リゾのビデオダンスは、事実やアクションとしてダンスの不在を提示する、“踊らないダンス”群とは一線を画す。
以上のように、<ヴィデオラマ>では、ユインというアーティスト個人と、フランスのダンス・シーンが、どんな関心をめぐって動いているのかを知ることができた。同時に、ダンスについての実験と映像とが切り結んだ幸福な例と一緒に、映像のダンスに対する可能性が示された刺激的な企画だった。
■ そこにはないダンスを再生する? <ビデオサロン −地域のダンス->
先に記録映像と区別したビデオダンスが手元に乏しい中、筆者が担当したビデオサロンの1日目は、記録映像を見ながら地域の作家の魅力を語ろう!という趣旨でプログラムを組んだ。以下に、そこで伝えようとした魅力を中心にまとめてみたい。
■ コミュニケーション 地域のダンスの魅力
この地域で生み出されるダンスの魅力は、もちろん単一の切り口では語れないが、どれか1つに絞るならば、断然コミュニケーションだ。
ここでコミュニケーションとは、制度や慣習やシステムによって生み出された境界線を越え、区別された領域や分断された人々が結びつくこと、くらいに考えている。そんな魔法を劇場で体験させてくれる、信頼できるアーティストがこの地域には多くいる。そのことを伝えるために、まずはステージダンスのルーツに関わる2つのダンス場面から始めた。ジョン・クランコの『ロミオとジュリエット』と、クルト・ヨースの『幼女の死にたむけたパヴァーヌ』の舞踏会の場面だ。いきなり地域とは何のつながりもない過去の作品映像に、訝しんだ来場者も多かったことだろう。だが、踊る者と見る者の間のコミュニケーションの試みに焦点を当てるなら、その間に横たわる見えない境界線の存在と成り立ちを知っておいて損はない。集団に和しない個性を価値あるものとして不特定多数が鑑賞できるのは、舞踏会に見られるような社交性の切り離しを含む、見えない条件付けが劇場制度に埋め込まれてきたからでもある。
地域の作家が、このような劇場での、踊る人と見る人の間の領域の住み分けに安住しないのは、一つには、路上やカフェなど、この線引きの流動的な場で踊る体験が豊富にあるからかもしれない。そう考えて、まずはモノクローム・サーカス作品と、そのサイド・プロジェクトである「収穫祭」の、初期の路上ダンスの映像を見た。次に、劇場で舞台と客席の間にある見えない壁、つまり、舞台の上で演じる者と現実を抱え客席に座る者の間の超えられない境界線を主題化して突き破ろうとする試みがgraggioの『壁』だ。これは映像作品としても舞台の臨場感を伝えることに成功している。そして最後に、j.a.m. dance theatreの『フィカスと虫、フィカスとロモコス』。ダンサーたちが、繰り返し倒れる中で、舞台の上の虚構のイメージを破り生身の人間として目の前にいるかのように感じられる状態に変容してゆく場面を長めに見た。
■ 作家の歩みを時系列に振り返る 山下残の魅力
後半は、一人の作家の創作の流れを時系列でたどるために映像を用いた。シリーズ化を考えているこの試みの第1回目のゲストは、山下残だ。しばしば言われるように、よい作家は作品のクリエーションごとに自分にとっての問いを突き詰め、その過程で新たな問いを見つけ出すが、山下の活動にも、そういった作品間の有機的なつながりを顕著に見て取ることができる。大まかに分けると、一つはコレオグラフィーというテクスト生成のための方法論に関わる変化で、ことばを試金石として振付を捉え直した書物三部作に端を発していまだ展開中。もう一つは、このコンセプチュアルに練り上げられたテクストの身体化に関わるもので、今年に入ってから発表された作品[『動物の演劇』と『船乗りたち(陸地バージョン)』]では、一つの到達点が示されたように思われる。このような大きな主題への取り組みの流れや前後の作品との連関を見つけてゆくことは、それだけで見ると奇抜さが表に立つコンセプトを支える必然性を知り、ひいては劇場での鑑賞体験を豊かにするのに役に立つのではないだろうか。
後半のもう一つのねらいは、過去の作品を作家自身のことばで語ってもらうことにあった。その中で、2000年前後を境として、自分の身の回りの小さな物語を紡ぐことから、より大きな連関に向かうようになったといった、ここで紹介した作品以前からの流れを知ることができた他、通常のダンスの成立条件と結びついている振付家とダンサーの間にあるヒエラルキーや、作家の内面の表現という伝達モデルを否定することと結びついたダンスのデータ化という構想など、作品ごとの方法論にとどまらない、山下の根本的な問題意識をかいま見ることができた。
■ ビデオサロンの今後
以上のように振り返って来たビデオサロンの1日目は、映像とともに、それについて語ることばの占める割合が高い催しとなった。今回は、諸々の事情で語り手は1人というセッティングを行ったが、将来的には、アーティストと来場者双方の間のダイアローグが成立するような工夫をして、映像を手がかりにダンスについてわいわいとおしゃべりする楽しさに、足を運んでくれる人を巻き込んでゆければと考えている。一回性の芸術であるダンスは、映像などのメディアによる記録に残すだけでは文化財としての価値を発揮しないが、記録メディアを手がかりに新しいクリエーションに利用されることで、作品の価値は新たに生み出される。語り直すということもまた、そういった再生行為につうじる意味を持ちうるのではないだろうかと考えている。
(文中敬称略)
|
|
|

|